Brionglóid
愛しの君に剣の誓いを
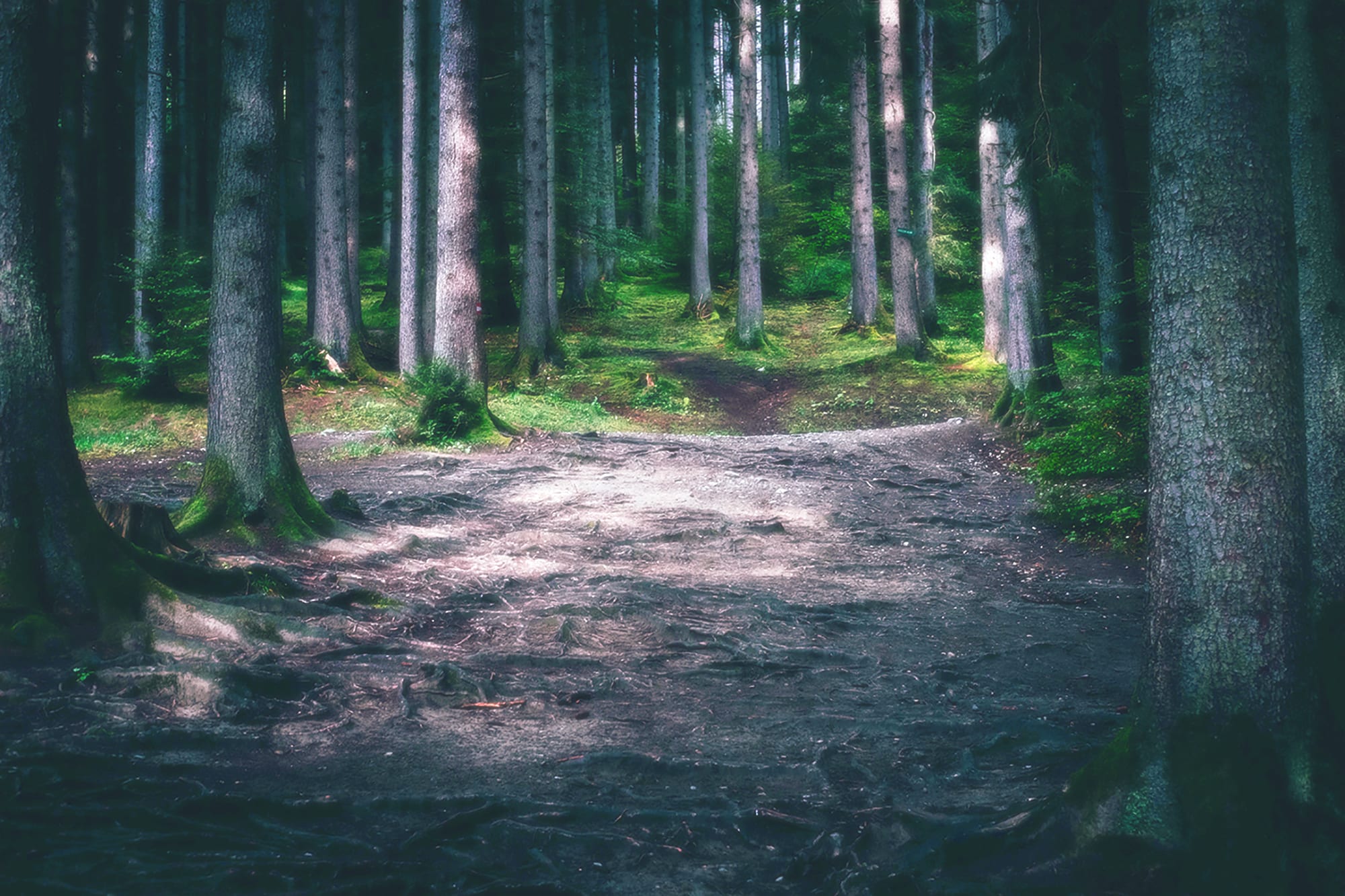
11
こほん、とひとつ咳払いをして、真実を告げたのは次兄クラレンスだった。
「……言っておくが、ラスティは正真正銘、男だ」
「嘘ッ!?」
「嘘って……」
思い切り意外だったという態度を取られては、ラスティも反論する気力すら萎えてくる。
事実を聞いてもまだ信じられないといった表情で、ローザはラスティを見つめた。
「え、だって……どう見たって女の子じゃない! 騙されたわ……!!」
「あのねえ! 僕、最初から隠してなんかいないんだけど! だいたいこんな格好で『僕』っていってたら普通女だなんて思わないだろ?」
「だってあなた、騎士を目指してるって言うから……」
女性であるという意識や甘えを捨てるために『僕』といっているのだと思った。
青褪めながらローザがそう言えば、その隣のアンディまで困惑した様子を隠さずラスティの顔をまじまじと眺める。
「私もてっきり、男装の少女かと……」
「いや、あんたにだけは言われたくないと思うぞ……?」
俺もさっきまで気づかなかったしな、と呟くウェインに、今度はラスティが怪訝そうな顔をした。
「……どういうこと、兄さん?」
「お前と逆なんだ、こいつは」
「へ?」
では、このアンディは……。
恐る恐る振り向いたラスティに、観念したのだろう、ひとつ嘆息してからアンディはきっぱりと告げた。
「アンドリューとは、姫の騎士としての名。だがこの世に生を受けた時、私は両親からアンドレアという名を授かりました」
「あんどれあ……」
この、クラレンスと張るくらい優美な美剣士が、女……。
兄達と共に戦って、実力的にも外見的にも遜色ないこの騎士が、女。
いろいろな意味で、ラスティは衝撃を受けたのだった。
「私は姫をお守りすると誓った時、自分の女の部分を捨てたのです。ですから、これからも男として生きていくことに躊躇いはありません。姫を守れるのは、今のところ私だけだと自負しておりますゆえ」
ローザに言い寄る騎士達がことごとく蛮族に負けてしまったことで、尚更アンディはその決意を固めたのだろう。このアンディが女だというのだ、ならばローザの目にラスティが女に映ったとしても無理はない。
「私は、せめてアンディと同じかそれより立派な騎士と結ばれたいのよ。父上もその言い分を認めてくださったわ。そんなに高望みじゃないはずよ、女性のアンディでここまでやれるのだから」
なのになんで、と拗ねたようにローザが呟く。不幸なことに、夢見るローザ姫の前には、アンディ以上の騎士が現れたことは一度もなかったわけである。この美剣士は、容姿も腕も忠誠心も、騎士として優秀すぎたのであった。
「ああでも! やっぱり納得がいかないわ! ラスが男だなんて! せっかく年の近いお友達が出来たと思ったのに……」
「……ごめん」
「アホ。お前が謝ることじゃないだろうが」
あまりに悲痛な表情のローザに思わず謝ってしまうと、心底呆れた様子の長兄が弟の頭を軽く叩いた。
「まあ、今のお前は確かにちまっとしてて可愛いが、二、三年もすりゃいい男になる。そん時に見返してやりゃあいいのさ」
ウェインがそう言うと、クラレンスも大真面目に頷いている。
しかしラスティは俯いた。
「……なれるかな、兄さん達みたいに」
「当然だろ。ちょうどいいお手本が目の前にいるんだぜ?」
相変わらずなウェインの言葉にラスティは笑ったが、そこで冗談じゃないと声を上げたのはローザだった。
「待ちなさいよっ。困るわそんなの! ラスが将来あなたみたいになるだなんて!」
「なんだ、文句あるってのか?」
「大有りだわよ! 妖精を魔物にすると聞いて、普通黙っていられて!?」
「ひ、姫っ」
果敢に食って掛かる姫君を、アンディが慌ててたしなめる。
しかし当のラスティはこれまでのやり取りをずっと見てきた上で、実はウェインとローザは案外いいコンビなのかも、なんて思った。二人にバレたら、それぞれからさぞかし怒られるだろうけれど。
「ごめんなさい、失礼なこと言って。ああは言ったけど……私は今のラス、好きよ。それは本当なの」
口喧嘩を中断させたローザは振り返り、そう言ってにっこり微笑んだ。
悲しいかな、恋する少年はそれだけで条件反射的にときめいてしまうのだった。
「改めてお友達になってくれるかしら、ラスティ。男の子だったのは意外だったけど、ラスはラスだもの」
「う、うん……」
赤面した末弟に、ウェインもクラレンスも苦笑を浮かべた。
「さて、追っ手が来る前に行きますかね。お姫様が一緒じゃあそうそう野宿ってわけにもいかねえし、早いとこ宿探ねえとな」
そう言って手綱を握りなおした長兄を、ラスティは驚いたように見つめた。
「え、じゃあ……」
「一緒に行ってやるよ。王都まで、な」
ローザとアンディの二人も、一斉にウェインを見た。居心地悪そうに鼻の頭を指で掻きながら、ウェインは言った。
「事情が事情だからな。ま、俺達もどうせセスナバルには行くつもりだったんだ。ちょっと予定が早まったと思えば、大したことねえよ」
もちろん、その分の報酬はしっかり国王からふんだくるつもりのウェインである。が、素直な末弟は心から兄に感謝したのだった。
「有り難う、兄さん!」
王都は遠い。その間、ローザと一緒にいることが出来る。その事だけで、もう心が浮き立つ感じがした。
旅は始まったばかり。少年の恋も、今、始まったばかりだ。
Fin.